
就職しようと思っているけど、求人サイトを見ていてもピンとこない・・・。

合わない会社は避けたいんだけど、まともな会社って、どうやって見つけたらいいの・・・?
そんな風に悩んでいませんか?
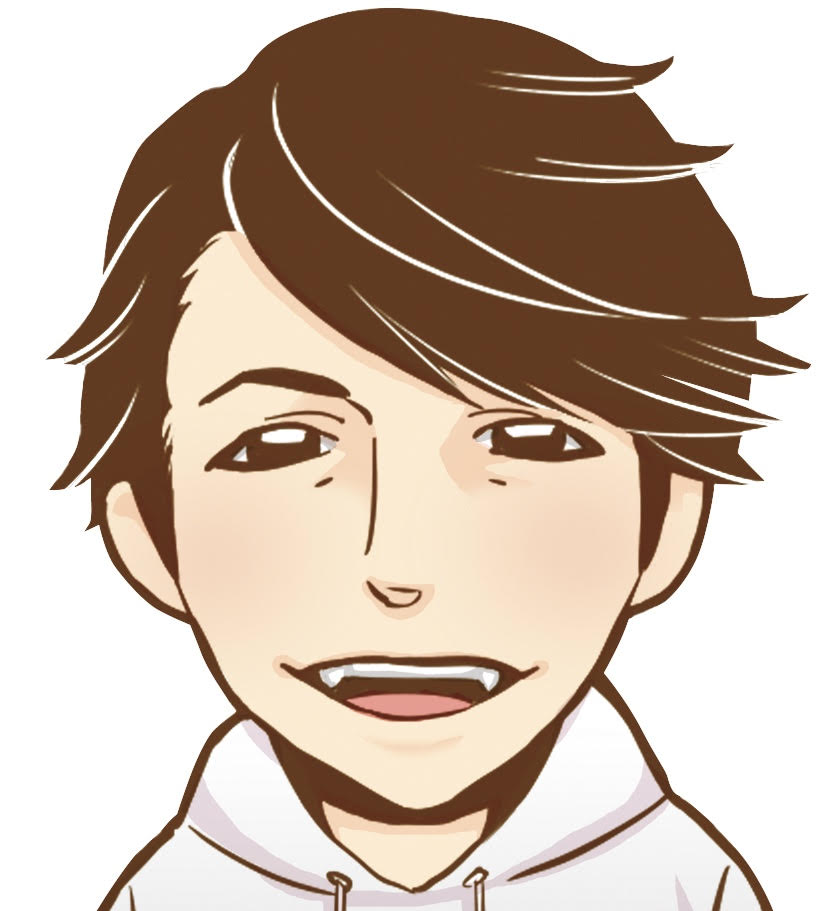
この記事は、自分自身フリーターから正社員になって10年、キャリアアドバイザーとして8年で3000名以上の就職サポートの経験がある私が書いています。
読むことで、自分に合った求人の探し方が理解できるようになり、仕事選びの悩みが激減します。
ぜひ最後まで読んでください!
まともな求人を探す前に、やるべきこと
求人の探し方について、早速解説をしたいのですが、その前にやるべきことを3つあげておきます。
・就職で叶えたいことを(ある程度)明確化する
・ゆずれない条件をしぼる
・業界と職種の違いを理解する
それぞれ、順番に解説しますね!
就職で叶えたいことは何かを、ある程度明確にする
まずはざっくりでも大丈夫なので、今回の就職で何を叶えたいのかを言葉にしましょう。
なぜ、これを最初にやるべきかといえば、就職活動の軸(会社選びの基準)が決まるからです。
軸(基準)が決まっていない状態で求人サイトをいくら見ても、なにも進みません。
むしろ、迷ってしまいます。
その状態で就活を続けても、納得感がなく、仮に内定が出たとしても良し悪しの判断ができないんですね。
だからこそ、最初の時点で、取り組むべきなんです。
もし、叶えたいことはなにかについて、答えるのが難しいなら、「なぜ就職したいのか」でもよいでしょう。
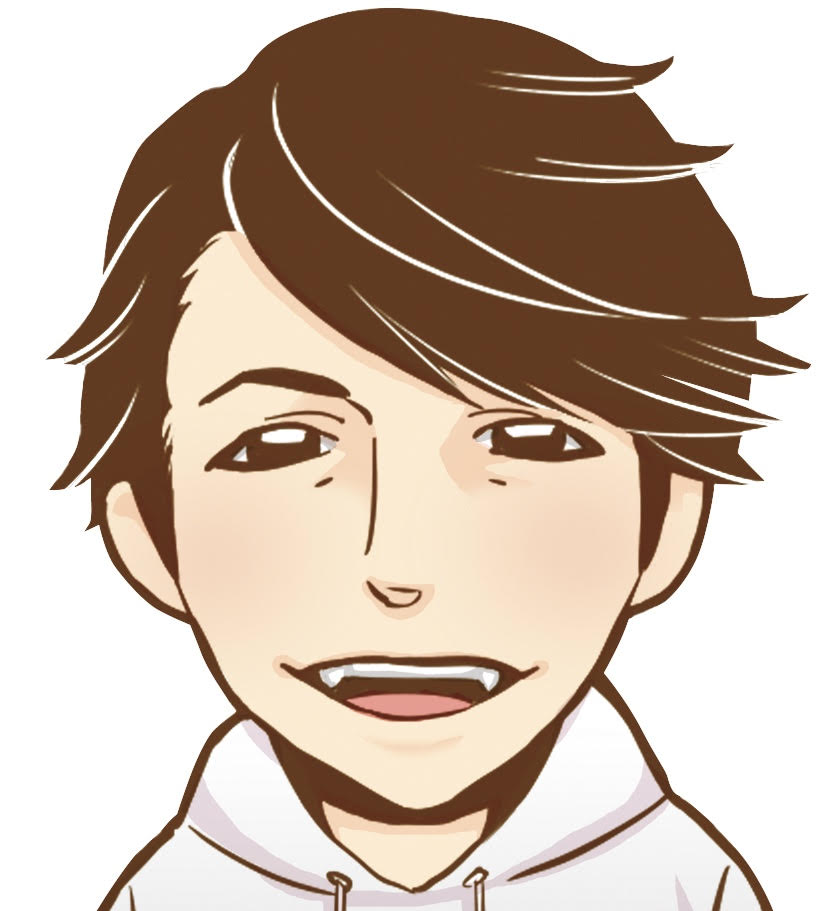
スマホでもパソコンでも手帳でも、なんでもOKですので、まずは言葉にしてみてください。
それが、あなたの「就活の軸≒会社選びの基準」になります。
ゆずれない条件を決めておく
続いて、似たような内容になりますが、とっても大切なことです。
求人を見ると、給料、仕事内容、福利厚生、企業規模、リモートワークの可否など、さまざまな情報があります。
その中でも、自分が絶対に譲れないものを、1つにしぼってください。多くても2つまでです。
なぜなら、社会人経験やスキルがない中で、自分の希望の条件を全て叶えるのは、現実的ではないからです。
仕事探しは例えるなら、不動産でのお部屋探しに似ています。
・日当たりがよい
・駅から近い
・間取りが広い
・上層階
こんな感じで、条件がたくさんあると、当然ですが家賃が高くなりますよね?
仕事探しや就職活動も同じことです。
・給料がいい
・リモートができる
・大手企業である
・福利厚生がいい など
希望条件があればあるほど、それに見合ったスキルや実績を求められます。
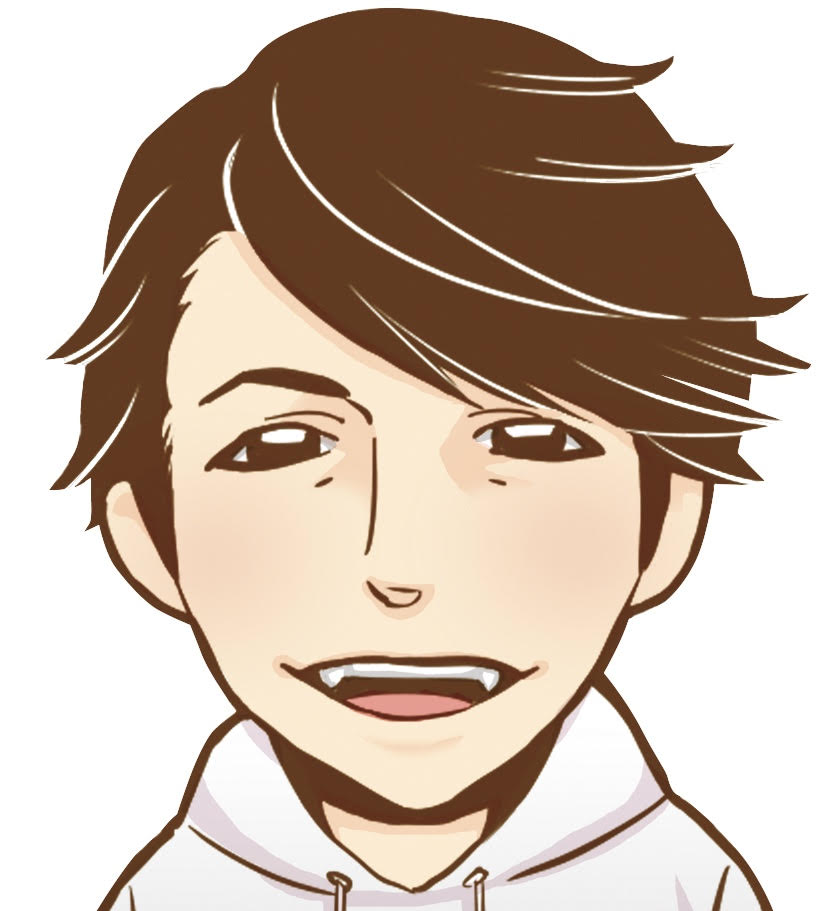
あれもこれもとなってしまうと、結果的に何も手にすることができないなんて怖いことにもなりかねないので、条件をしぼっておくことが大切なんです。
業界と職種の違いを理解する
就職時のミスマッチの可能性を減らすために、業界と職種の違いを理解しておくことも大切ですね。
業界と職種の違いがわかる人は、このパートを飛ばしていただいても問題ありませんが、分かりづらい人もいると思いますので、簡単に説明します。
●業界
グループ、ひとつの大きなくくり
(例:飲食業界、医療業界)
●職種
グループ内での役割
(接客・調理、医師・看護師など)
簡単にいえば、こんな感じです。
仕事を探す際に、業界と職種のどちらを見るべきかは、人によって違うかと思いますので、それぞれのメリットとデメリットも書いておきます。
| メリット | デメリット | |
| 業界 | (広くいえば)自分の興味があるサービス、商品に携われる | 必ずしも希望通りの部署や職種で採用されるわけではない |
| 職種 | 仕事内容が決まっているため、イメージがしやすい | 事業内容によっては、興味がない分野で働くことになる |
上記を踏まえたうえで、筆者のおすすめをお伝えすると、フリーターや既卒の方が就活をする際には、職種をメインに見た方がよいです。
理由を3つ挙げておきます。
・業界での就職は新卒時の総合職採用がメインであり、フリーターは対象外になることが多い
・入社してから行う仕事は「職種」であり、業界で選ぶとミスマッチになる傾向がある
・職種での経験を積むことで、将来的に「興味がある業界×自分の経験が活かせる職種」で働ける可能性がある
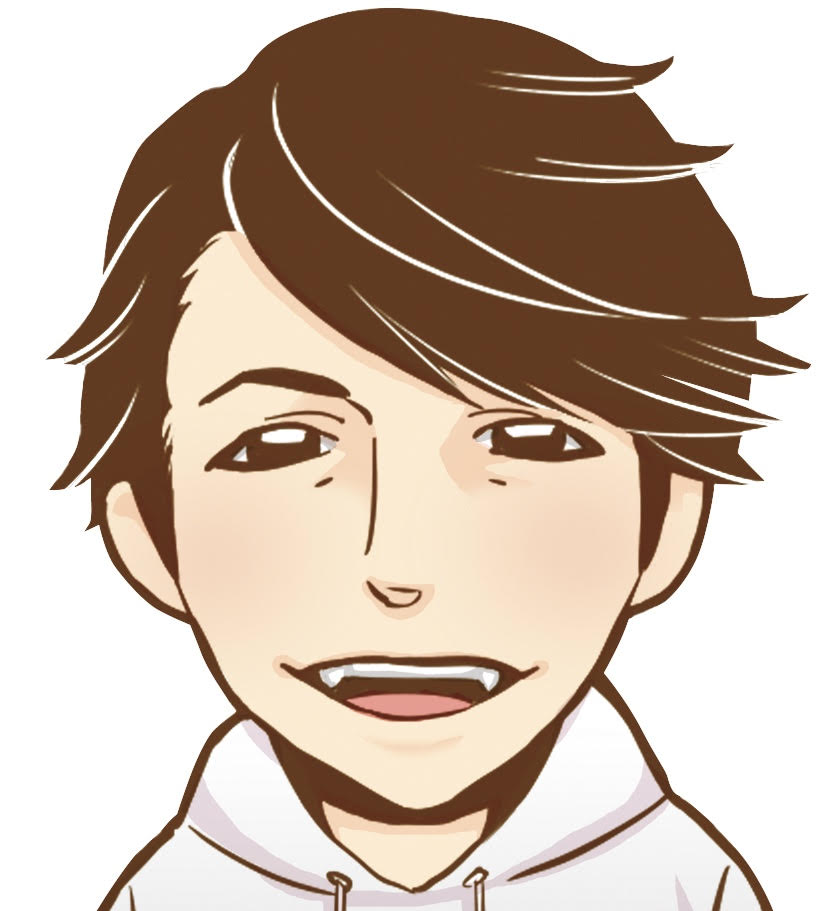
入社してから「思っていたのと違う・・・」ってご相談は、業界と職種の違いがイメージできていないケースでの「あるある」です・・・。
まともな求人を探すための3つの方法とメリット・デメリット
ここからは、求人を探す代表的な方法3つと、それぞれの特徴について解説します。
まずは、内容をまとめた表を先に貼っておきますね。
| 仕事を探す方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ハローワーク | ・全国どこのエリアでも相談所がある ・地元の求人が多い | ・求人情報が古かったり、事実と違うケースもある ・担当者が年配で人によっては相談しづらい |
| 求人サイト | ・たくさんの求人を見れる ・マイペースに就活を進められる | ・情報が多すぎて、迷う ・自分に合った求人を選ぶのが大変 |
| 転職エージェント | ・自分に合った求人を、プロの目線で提案してくれる ・自力だと内定獲得が難しい会社でも内定が出るようサポートしてくれる | ・担当者の当たりはずれがある ・ごり押ししてくる担当者や会社も、実際問題として存在する |
では、それぞれ順番に説明していきます。
ハローワーク
まずは、おなじみのハローワークです。
だいたいの場合、お住まいのエリア近くにあると思いますし、一度は行ったことがある人も多いのではないでしょうか。
ハローワークで仕事探しをする、メリットとデメリットをあげておきます。
●ハローワークのメリット
・全国どこのエリアでも相談所がある
・地元の求人が多い
●ハローワークのデメリット
・担当者が年配で、人によっては相談しずらい
・情報が古かったり、一部事実と違うケースがある
ハローワークは、地元で働きたい人におすすめです。
なぜなら、求人サイトで探した場合、お住まいによっては県外への転居や転勤が必要になる会社もヒットしますが、ハローワークは地元のみで働ける求人をメインにあつかっているためです。
ただ、ハローワークの求人票に書いていることと、面接や採用時に聞かされる内容が違うってこともあるようなので、その点は注意しておいたほうがいいでしょう。
ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~「なぜハローワークから嘘の求人がなくならないのか」https://www.hwiroha.com/uso.html(2025年1月21日)
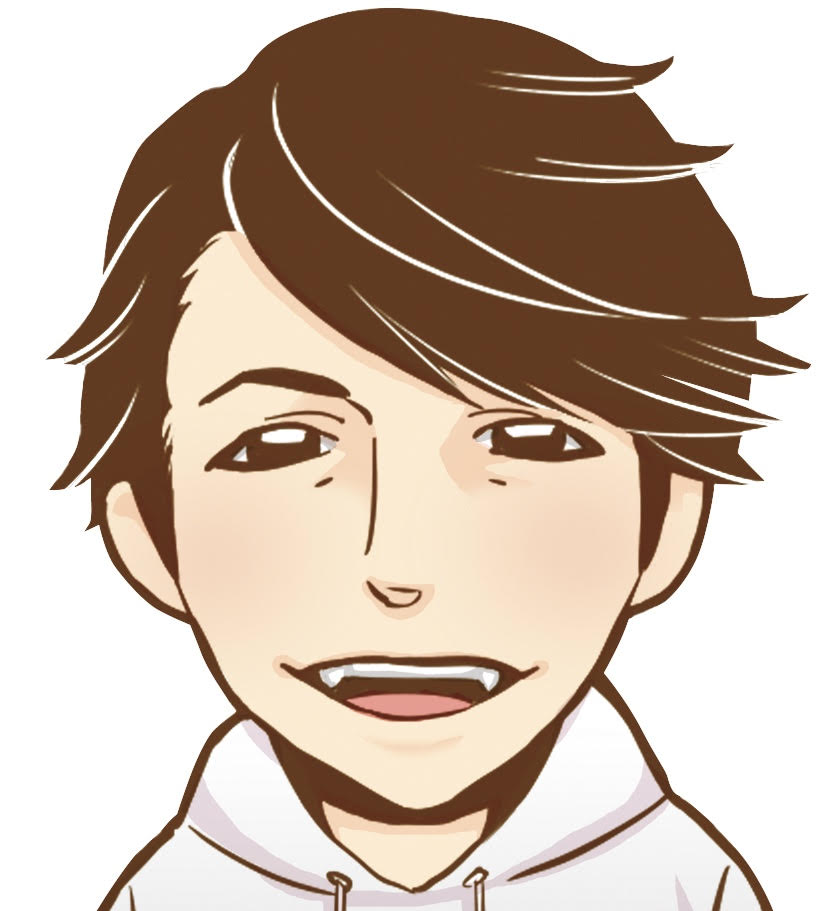
求人票に嘘を書くような会社は本当になくなってほしいですが、すぐに解決できる問題ではないことも確かなので、自分自身でしっかりと事実を確認する必要がありますね・・・!
求人サイト(ネット検索)
つづいて、リクナビやDODA、Indeedなどの求人サイトです。
スマホで求人検索すれば、だいたい最初の方に出てくると思うので、使ったことがある方も多いと思います。
求人サイトのメリットとデメリットをあげておきます。
●求人サイトのメリット
・求人情報の数が多い
・マイペースで進められる
●求人サイトのデメリット
・情報が多すぎて、逆に迷ってしまう
・自分に合った求人なのか、判断するのが難しい
求人サイトは、求人情報をたくさん見たい方におすすめです。
なぜなら、リクナビやDODAなど、大手が運営しているサイトであれば、ほかと比べても求人数が圧倒的に多いからです。
また、求人サイトをつかった就職活動は、自分のペースで進めることができるのもメリットで、とくに就活に慣れている人にとっては良い選択肢でしょう。
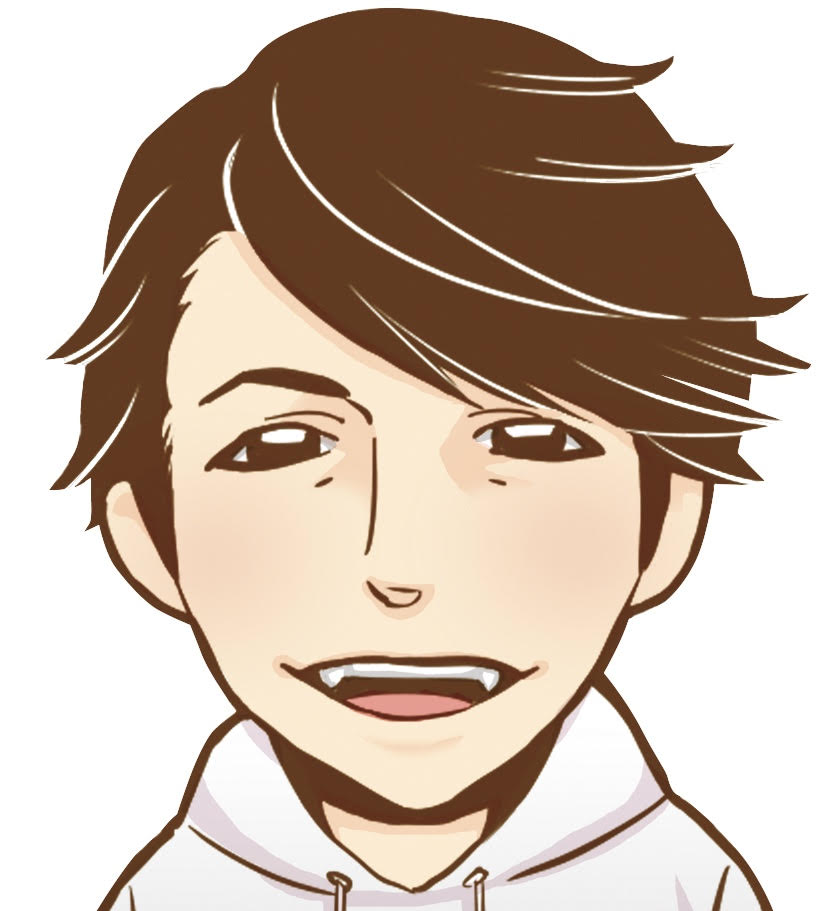
求人情報が多すぎて迷ってしまうケースも多発しているので、最初にお伝えした「就活の軸」を明確にした状態でサイトを見るようにしましょう!
転職(就活)エージェント
もうひとつが、転職エージェントを使う方法です。
転職エージェントは、担当者が求職者の話を聞いた上で、おすすめの求人を紹介してくれます。
無料で相談できますし、フリーターや既卒の方に特化してサポートしている会社も、最近よく目にしますね。
エージェントのメリットとデメリットをあげておきます。
●転職エージェントのメリット
・自分に合った仕事をプロの目線から紹介してもらえる
・自力だと内定獲得が難しい会社でも内定が出るようサポートをしてくれる
●転職エージェントのデメリット
・担当者によっては、サービスの質が低いこともあり得る
・自分が納得していなくても、ごり押ししてくる担当者も実際まれにいる
転職エージェントは、就職活動のやり方や、自分に合った仕事がわからない人におすすめです!
なぜなら、担当者は転職のプロとして、あなたの話を聞いたうえで、お勧めの求人を紹介してくれるからです。
また、求職者の方が無事に成功することで、転職エージェントは利益が上がるため、自力だと内定獲得が難しい会社でも内定を勝ち取れるサポートを全力でしてくれるのも大きなメリットです。
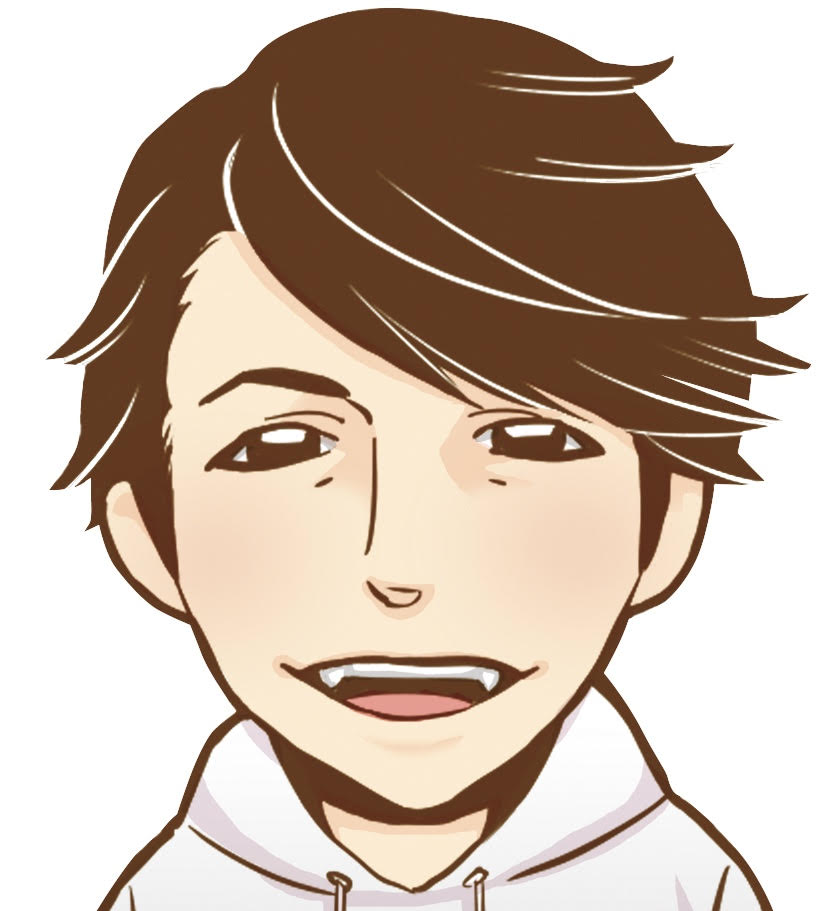
ただ、担当者によっては良くないこともあるので、そのときは「担当者を変えてほしい」と伝えればOKです。言いづらいとは思いますが、就職は人生の一大事なので遠慮は妥協はなしでいきましょう!
ここまでの内容をふまえたうえで、筆者のおすすめとしては、求人サイトとエージェントの同時利用です。
自分で求人を探しつつ、プロから客観的な意見や、場合によってはサポートをしてもらいながら就活を進めていくことで、1人で進めるよりも良い結果になる可能性が高まりますので。
なお、転職エージェントの使い方、見極め方については本記事の後半に軽く触れていますので、あわせて参考にしてください。
大切にしたい項目ごとに分類した、求人で見るべきポイント
ここからは、考え方や価値観ごとに重視したい項目をタイプ別に分けて、求人を見る際のポイントを解説します。
ざっくりと分けると、4つのタイプがあります。
・収入
・ワークライフバランス
・安定
・やりがい(仕事内容)
ちょっと見づらいのが難点ですが、求人票の見方については、厚生労働省が出している情報が確実というかスタンダードになるので、あわせて参考にしてください。
厚生労働省「求人票の見方」https://www.mhlw.go.jp/content/000616349.pdf(2025年1月21日)
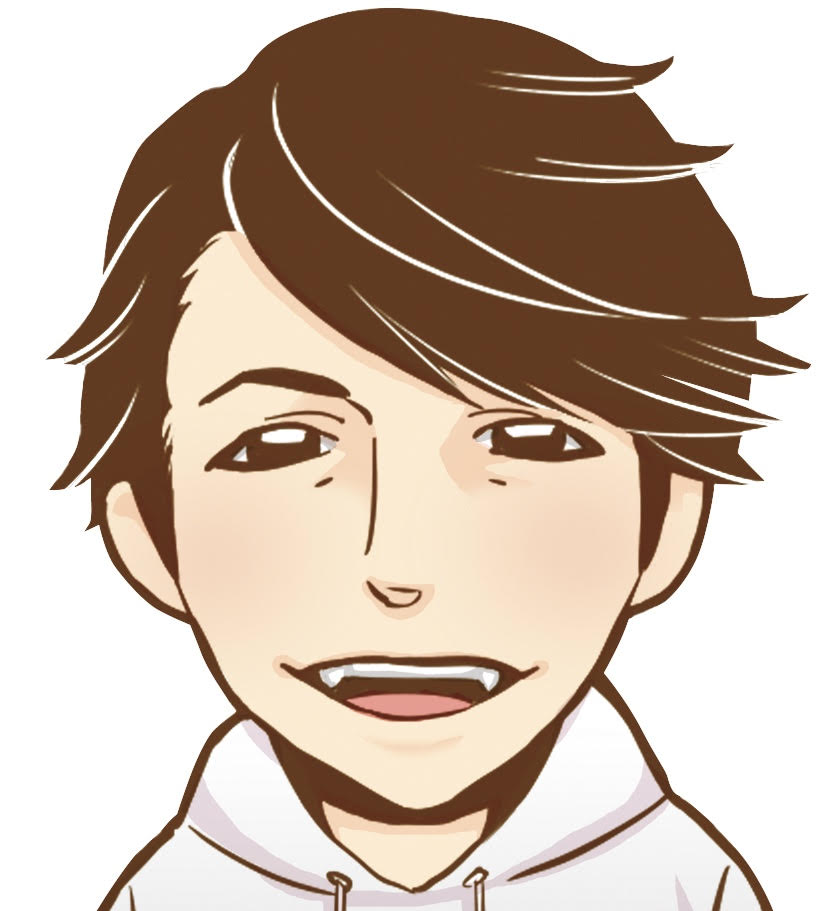
こまかい内容じゃなくて、ざっくりと理解したいって人は、これから解説する内容で全然OKです!
収入重視の場合
給料(賃金)、手当の部分をメインで確認しましょう。
具体的にあげておきます。
・基本給はいくらか
・各種手当(営業手当、住宅手当、通勤手当など)は出るのか
・賞与(ボーナス)はあるか。あるとしたら何カ月分か。
・固定残業はあるか。あるとしたら何時間か。
・昇給はあるか。実際どれくらい上がるのか。
・インセンティブはあるか(主に営業職)。
このあたりは、絶対にチェックです。
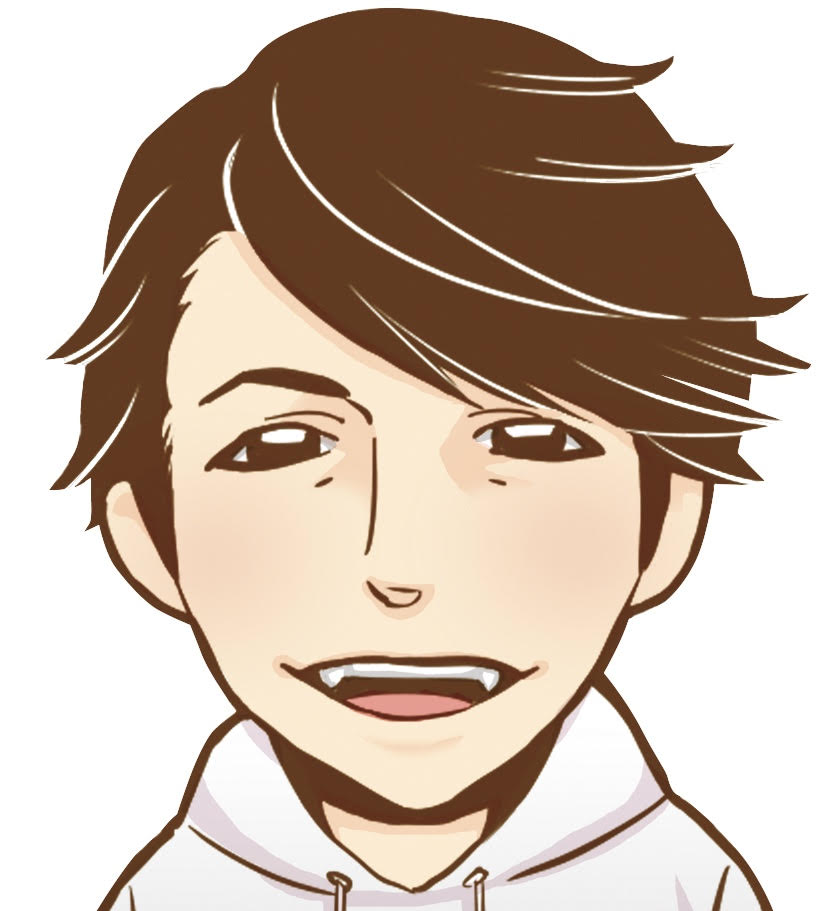
ちなみに、固定残業代がついていたとしても、絶対に残業しないといけないってわけではありません!
仕事が終わっていることが前提にはなりますが、ほとんど残業せずに帰れた場合でも、固定残業がついている分もらえますので、人によってはトクします。
とはいえ、仕事量が多い可能性もありますので、その点は注意して確認した方がいいでしょう。
ワークライフバランス(働き方)重視の場合
つづいて、ワークライフバランスを大切にしたい人が見るべきポイントです。
・就業時間
・時間外労働の有無
・年間休日数
・就業場所
上記をメインで確認しておきましょう。
通勤時間はどれくらいか、リモートワークはできるのか、完全週休2日なのか、平均残業時間はどれくらいかがチェックポイントになりそうですね。
なお、平均残業時間については、行政と民間企業で出しているデータに相違がありますが、いわゆるホワイト企業の目安としては、月間の残業時間が20時間以下の認識でOKです。
厚生労働省「毎月勤労統計調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/23fr/dl/pdf23fr.pdf(2025年1月22日)
DODA「平均残業時間ランキング【91職種別】」https://doda.jp/guide/zangyo/(2025年1月22日)
厚生労働省だと10時間、DODAだと21.9時間とのことです。
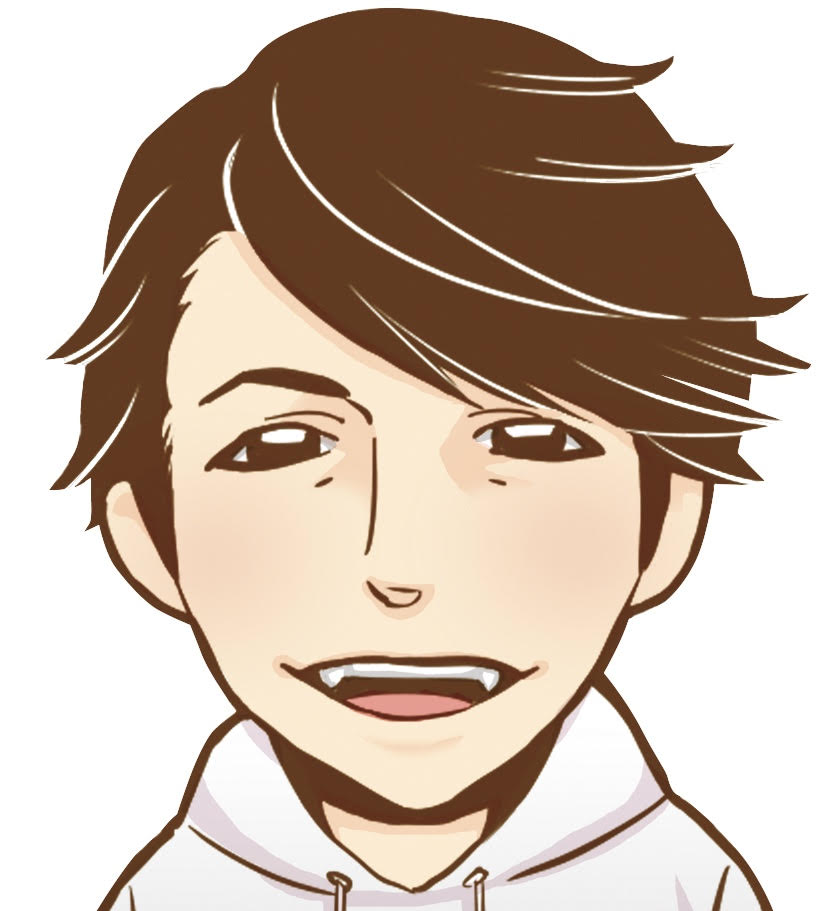
就職や転職の相談に乗っている身としてはDODAの数字の方が実態に近いと考えていますので、ワークライフバランス重視の人は、残業時間が20時間以内の求人をチェックするようにしましょう!
安定重視の場合
従業員数、設立年、資本金、労働組合の有無などを確認しましょう。
いわゆる大手企業とは、従業員数が1000人以上、資本金1億円以上の会社だと理解しておけばOKです。
安定を重視する人にとっては、会社がなくならないかどうかが気になる点だと思いますので、上記を参考にしてみてください。
ただ、終身雇用は崩壊したと言われている現代において、社格を重視した就職活動は、本来の意味での安定から離れてしまう可能性が高いので、個人的にはおすすめしていません。
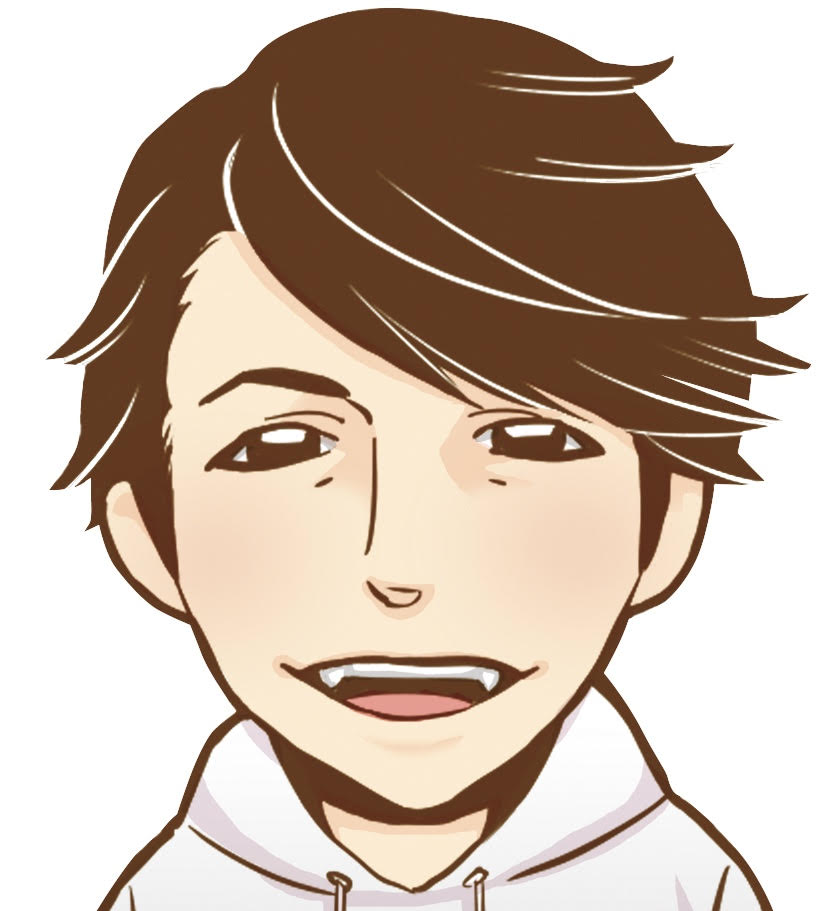
本当の意味での安定とは「スキル」を身に着けることで、もし会社がなくなったとしても転職できる状態を当サイトでは定義してします!
やりがい(仕事内容)重視の場合
事業内容、職種、仕事内容をしっかりと確認しておきましょう。
求人票が具体的に書かれているか、それともあいまいな表現になっていないか、要チェックですね。
また、あきらかに未経験からでは厳しい内容(例:コンサルティング、マーケティング、人事)でも、未経験者募集と書かれている求人については注意が必要です。
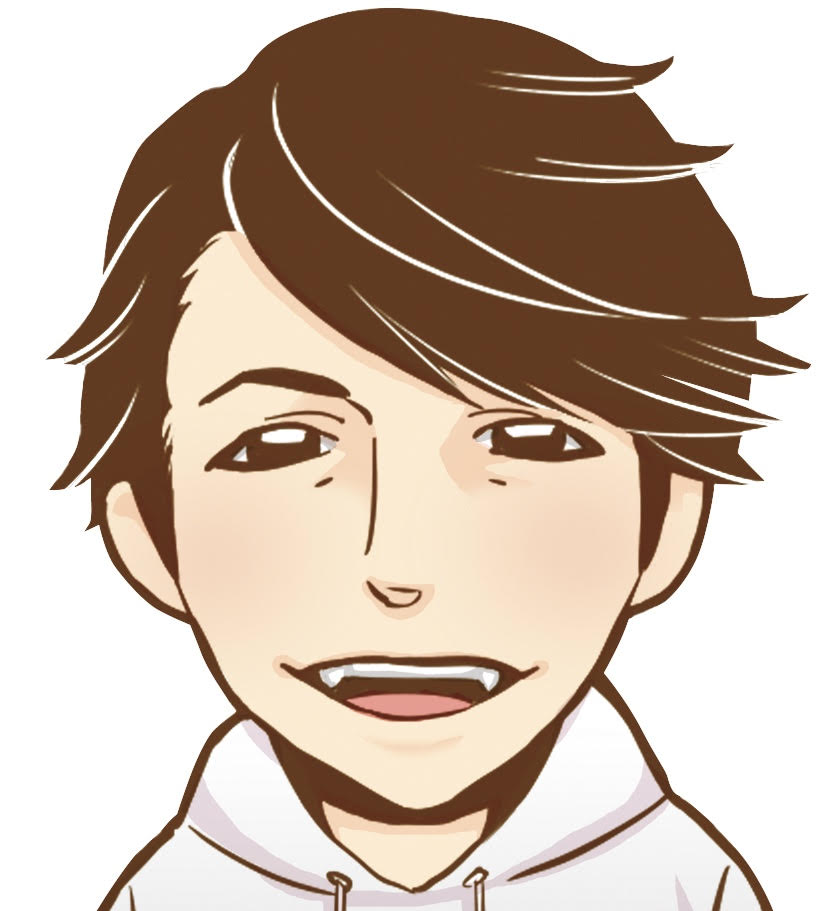
実際の仕事内容は「雑用」的なものや、離職率が非常に高い会社だったなんてことも実際よく聞くので、気を付けましょう・・・!
仕事内容をみるときは、これまでの自分の取り組み(バイト、部活動、ボランティア、学んできたこと)が活かせそうかどうかも、ある程度想像しておけるとよいですね。
求人票を見極めるときの良い例・悪い例
本章の最後に、求人票を見る際の注意点として、共通する見極め方をまとめておきます。
| 良い例 | 気をつけた方がよい例 |
| ・基本情報が具体的に書かれている(月給、休日、業務内容など) ・未経験募集の内容として常識的である(仕事内容、昇給額、上がり幅など) | ・あいまいな表現(応相談、横文字が多い) ・専門的なスキル、知識が必要なはずの募集 (マーケティング、人事、データサイエンティストなど) ・昇進が早すぎる(半年~1年で管理職など) ・昇給幅や給与額が大きすぎる(1年で100万UP、月給40万~など) |
雇用条件通知書は、必ず確認しておく【内定後の対応】
これは内定後のお話になりますが、非常に重要なので書いておきます。
内定をもらった後、「雇用条件通知書」が会社から渡されます。
だいたい、メールなどのオンライン上でのやり取りか、企業によっては紙で出してくれるもので、働く上での正式な条件がすべて記載されています。
書面を確認したあと、サインと印鑑を押すことで、その会社で働くことが正式に決定しますので、絶対に一字一句とばさずに読みましょう。
なぜなら、サインをした時点で書類に書いてあることが絶対となり、求人票の内容と違うことがあった場合でも、あとの祭りになってしまうからです。
かならず、自分の目ですべて確認して、納得したうえでサインするようにしてくださいね。
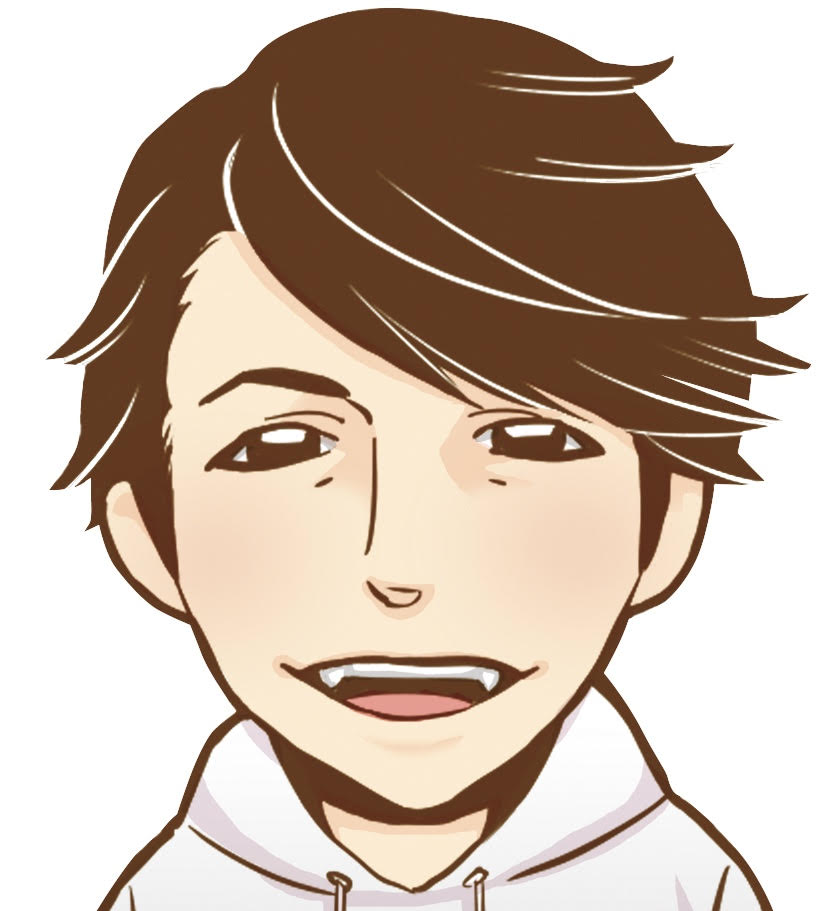
たまにもらえませんでしたってご相談を聞くこともあるのですが、そのような会社には、絶対に入社してはいけません。
まともな求人を探すなら、エージェントにも相談してみよう
タイプ別に分けた、求人の探し方まで解説してきました。
最後に、まともな求人を探したい人が、就職活動を成功させたいなら絶対に使った方がいい「転職エージェント」について触れておきます。
転職エージェントの利用は完全無料、いつでも利用中止することもできますので、気軽につかいましょう。
転職エージェントを使って就活をして、内定が出たらその企業で働かないといけないんじゃないですかって言われることがあるのですが、それは全くないです。
違うなと思えば辞退すればいいだけですし、本当によいエージェントなら、しっかりと相談に乗ってくれますよ。
おすすめのエージェントについては、下記の記事でくわしくまとめていますので、参考にしてください。
よいエージェントの見極め方5選(実体験から断言)
私自身、エージェントとして働いていました。
その実体験を踏まえたうえで、どんなエージェント(担当者)がいいのか、見るべきポイントを4つあげておきます。
時間を守る
遅刻してくるエージェントは、論外です。
一時が万事で、雑な対応をしている可能性が高いでしょう。
これは私がエージェントをやっているときに、最も気を付けていたことの一つでもありますが、時間を守らない担当者は変更するか、その会社の利用はさけた方が無難です。
レス(返信)が速い
何かしら問い合わせをしたときに、返信が遅いエージェントは信用できないでしょうし、不便です。
ただ、夜間(20時以降)とかは返信できなくても普通というか、責めるようなことではありません。
話を最後まで聞いたうえで、自分も気づいてなかった可能性まで提案してくれる
話を聞いてくれるのは当然のことなのですが、提案までしてくれるエージェントは、そう多くありません。
だいたいの担当者は、話を聞いて、希望する条件の仕事があるとかありませんとかで終わっちゃいます。
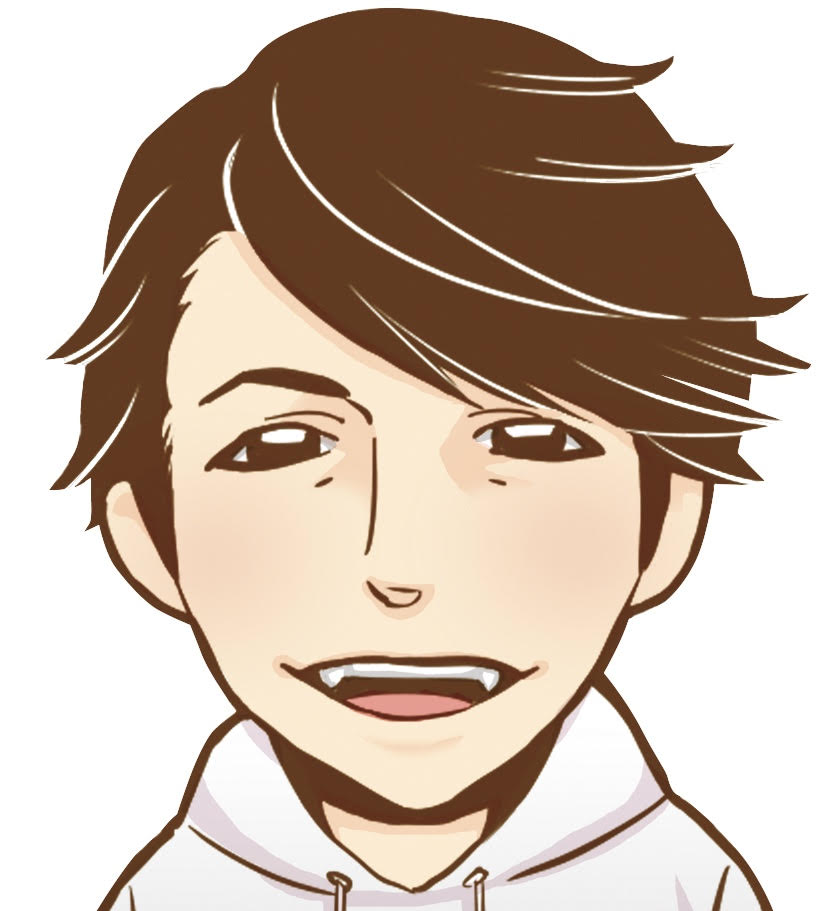
「○○さんなら、この仕事や会社がおすすめです」みたいな形で、しっかり納得できる理由をセットで教えてくれるエージェントなら、信用してみる価値は大いにあります!
良いも悪いも、選考結果とその理由を詳しく教えてくれる
これは非常に重要なポイントです。
書類選考や面接の結果が、いい方向でも残念なものでも、ちゃんと理由を教えてくれるエージェントは信用できます!
逆に、企業から聞けていませんとか、教えてくれませんでしたというような対応の場合には、担当者のレベルが低いか企業側との関係が良好ではないため、あまりよいエージェントとは言えないでしょう。
もし、どうしても聞けなかったり、聞いたとしても教えてくれなかったとしても、エージェントという就活のプロとしてはどう考えているのか意見をくれる人なら、信用してもいいと思います。
フリーターや既卒のサポートが強い会社(担当者)である
フリーターや既卒など、相談者のタイプに合わせて特化した会社を選ぶようにしましょう!
なぜなら、会社によって得意ゾーンがちがうため、フリーターや既卒の方が大手のエージェントだけを利用していても、丁寧なサポートは期待できないからです。
大手のサービスは求人数の多さが魅力ではあるものの、自分が応募できなかったり、条件に合っていなかったり、経験者向けの求人なども含まれているので、仕事探しが難航してしまう場面もよく目にします。
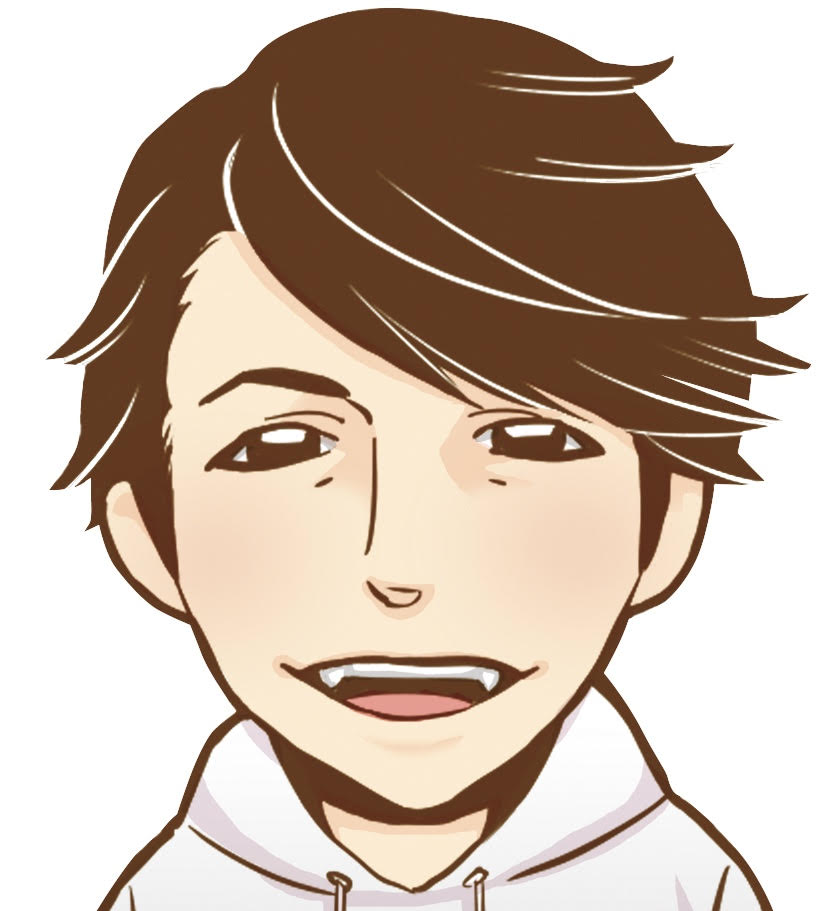
応募できないものや条件に合っていないもの含めて30~50社ほど送り付け、「気になるものは片っ端から応募しましょう」と雑な対応をされるなんてケースも・・・。
フリーターや既卒の方が就職をするなら、こんなエージェントがおすすめ
結論、内定獲得まで全力でサポートしてくれるエージェントがよいです。
なぜなら、フリーターや既卒の方が自力で自分に合った会社を選ぶことはもちろん、まともな会社で内定を勝ち取るのが最難関だからです。
具体的に、必要なサポートをまとめます。
・徹底した自己分析
・自己分析をふまえたうえで厳選した求人紹介
・履歴書と職務経歴書の具体的な書き方をレクチャー
・応募する会社に合わせた面接練習を納得するまで何度でも
・電話orオンライン面談+ラインやメールでいつでも相談可能
これらを、徹底的に伴走してくれる会社がいいです。
その中でもとくに、担当者自身がフリーターや既卒など、難しい状況から正社員就職に成功していたり、豊富な支援実績がある会社を選ぶとよいでしょう。
なかでも、個人的に一番おすすめできるのは、株式会社UZUZ(サービス名:ウズキャリ)です。
なぜなら、フリーターや既卒の人の「痛み」を理解できる人が作った会社であり、業界の中でも若者支援に力を入れて、事業を展開されているからです。
創業者が1社目を早期離職して就活で苦しんだ経験から立ち上げた会社で、支援実績も非常に豊富。
だからこそ、安心して相談ができるし、おすすめも心からできます。
●UZUZの主な実績
・就職支援実績 68,374名(2024/12/12時点)
・入社後の定着率 93.6%
・大手からベンチャーまで登録企業者数3,000社
念のため、UZUZに関する情報をまとめた表を貼っておきますね。
| 対象者 | 29歳までで、下記に該当する人 ・フリーター ・大学中退 ・既卒 ・就職浪人 ・ニート |
| エリア | 全国どこでも相談可能 |
| サポートにかける時間 | 平均12時間以上 |
| 内定獲得までの期間 | 平均1カ月(最短は1週間) |
| 求人数 | 3,213社以上(大手、ベンチャー、老舗まで幅広い) |
| 定着率 | 96%(2024年度実績) |
| 会社規模 | 164名 |
| 就職実績 | ●企業規模ごとの就職決定割合 ・1,000名以上 62% ・501~1000名 25% ・500名以下 13% ●就職者の例 ・フリーター→広告業界Web広告営業 年収270万円→420万円(25歳) ・コールセンターのアルバイト→メーカー企業の事務職 年収230万円→360万円(27歳) ・無職(ニート)→IT業界ITエンジニア 年収0円→350万円(28歳) |
| その他 | ・キャリアカウンセラーの9割が元既卒・第二新卒 ・社長がYoutube(登録者7万人)、SNSで発信している ・教育事業(IT分野メイン)、無料就活相談サービスまで展開 |
| 利用をお勧めできない人 | ・ハイクラス(年収600万以上) ・30代以上の人 |
就職支援実績はもちろんですが、エージェント経由で入社した方の定着率が96%は、率直にすごい。
定着率が高いってことは、「思っていたのと違う・・・」が少ないって意味でもあるので、安心して働ける会社に出会える可能性がそれだけ高い証拠になります。
ちなみに、日本全体の定着率は85%といわれています。
厚生労働省「https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf(P7)」(2025年1月22日)
また、在籍メンバーの9割がフリーターや既卒、大学中退からの正社員就職を経験している「フリーターや大学中退者領域のプロ」であるからこそ、話しやすくて信頼できるのもよいですね。
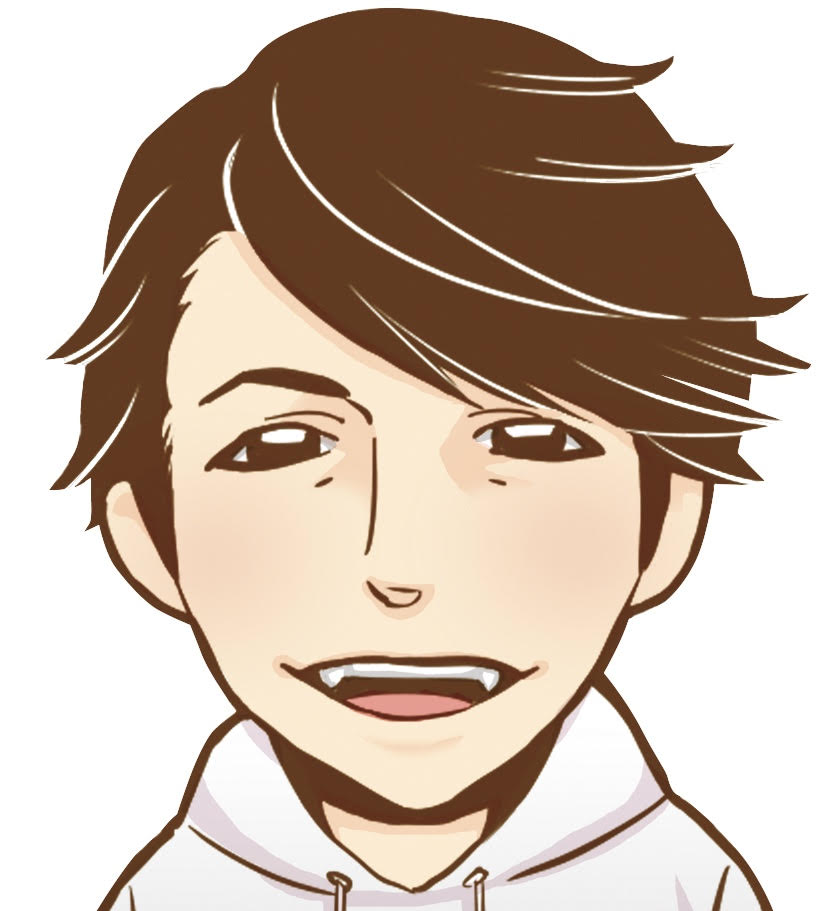
相談者ひとりにかけるサポートの時間は平均12時間と、他社と比べても圧倒的です!
※ふつうは初回面談から面接練習まで5時間~6時間ほど
少しでも興味をもった人は、相談だけでも親身に聞いてくれますので、ぜひフォームを入力してみてください(30秒で完了します)
担当の方がサービスの流れや今後のことを丁寧に説明してくれますので、サポートを開始するための許可(フォーム入力)をするだけです。
エージェントへの相談は、ちょっと勇気がいると思いますが、利用は完全無料で合わないならライン一通で退会も受け付けてくれます。
どうするかはご自身で自由に決められますので、自分に合った会社で安心して働きたいなら、いちど相談してみてください。
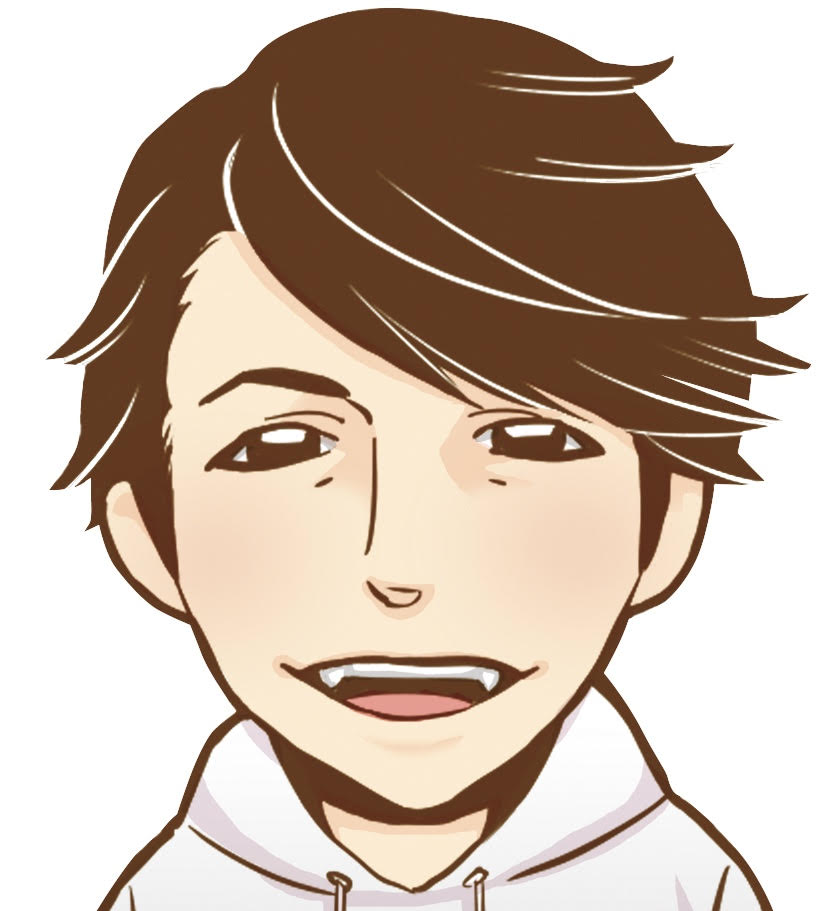
本当によいサービスなのでUZUZについて熱く語ってしまいましたが、ほかのおすすめエージェントについても知りたい人向けに、利用時の注意点やコツ、よくある質問をまとめた記事も貼っておきますね。
まとめ
まともな求人の探し方について解説しました。
●求人を探す前にやるべきこと
・就職で叶えたいことを明確にする
・ゆずれない条件を2つまでに絞る
・業界と職種の違いを理解する
●求人を探す方法を理解しておく
・ハローワーク
・求人サイト
・転職エージェント
●重視するものに合わせて、求人をみる
・収入重視
・ワークライフバランス重視
・安定重視
・やりがい重視
今日の内容を参考にしていただき、よい求人や会社と出会えることを、こころから応援しています!
行動こそが人生を変えてくれますので、まずはできる範囲で、いますぐ行動しましょう!
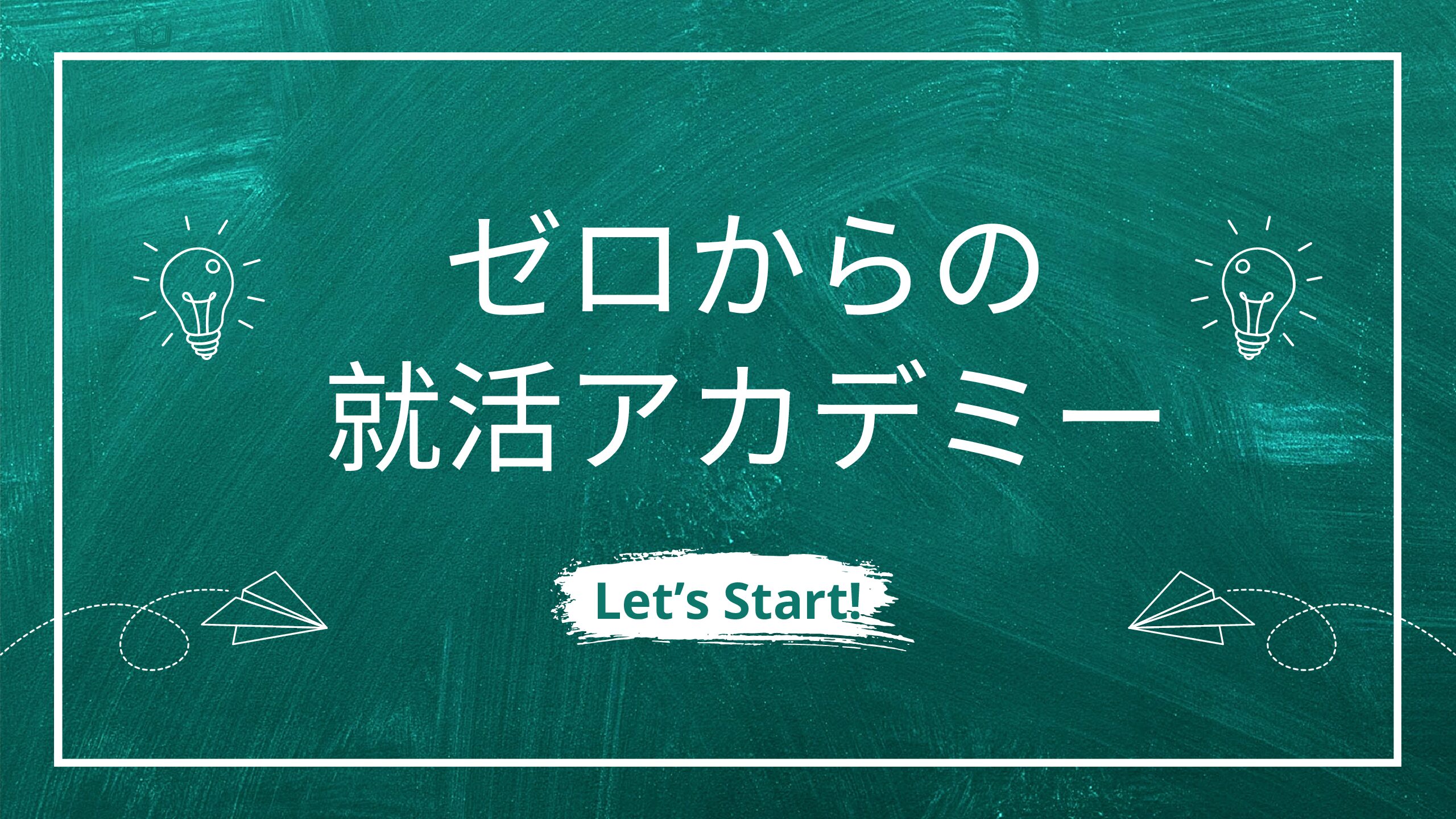

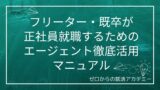

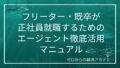
コメント